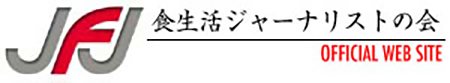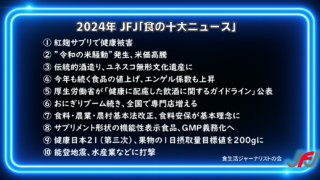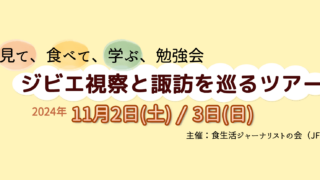講師:石島藤夫氏(農薬工業会安全対策委員長)
平成23年2月15日(火)、18:00~20:30
於:東京・丸ビル8階会議室
参加者:14名(+農薬工業会会員)
まとめ:佐藤達夫
平成22年度最後の勉強会は、農薬工業会との「情報交換会」を兼ねて、「農薬の安全性はどうなっているか」を、専門家に講義してもらった。第2部では質疑応答・意見交換が盛んに行なわれた。
■第1部 石島氏の講演の要約
農薬の安全性は、農薬取締法と食品衛生法という2つの法律で監視されている。農薬の製造、認可(法律では「登録」という)、販売、使用など、田畑で使われるまでは農薬取締法が、農産物(食品)となってからは食品衛生法が適用される。
この間、農薬(製品)の製造~販売までは農水省や農薬会社の責任で、使用段階では厚生労働省や農家の責任において、それぞれ監視が行なわれる。農薬の安全性の理解と正しい判断や消費行動は、消費者の責任であることも知っておいてほしい。
現在栽培されている農作物は、収穫量や味覚や栄養などを向上させるために育種・選抜された植物なので、けっして自然の植物ではない。また、農耕地も、単一植物を集約的に栽培するなど、自然の生態系とはまったく異なっている。そのため、農作物は病害虫にきわめて弱い。農薬は農業生産に欠かすことはできない。
農薬を使わないと、食料として充分な量が確保できないばかりではなく、アフラトキシンなど毒性の強いカビのリスクを減らすことができないため、農作物の危険性が逆に高くなることもある。もちろん、除草に要する労力の軽減も、農業者にとっては農薬使用の大きなメリット。
農薬の危険性は、大きく「急性毒性」と「慢性毒性」に分けて考えることができる。急性毒性は使用者(主として農業者)に対するリスクであり、慢性毒性は農産物を毎日食べる消費者に対するリスクだ。
消費者が気になる慢性毒性は、動物実験で得られたNOAEL(無毒性量)を100分の1にしたADIを根拠にして議論される。ADIというのは“食品中のある化学物質を、ヒトが毎日・一生涯にわたって摂取しても健康影響が生じないと推定される量”で、「一日あたり・体重1kgあたり」の「mg」で示される。
しかも、運用上は、ADIの80%以下の摂取量に抑えられるように「残留農薬基準」が定められているので、農薬による慢性毒性リスクは通常の食生活をしている限り考えられない。たまに「残留農薬基準値を超えた農作物が見つかった」という発表があるが、それを口にしたからといって、健康被害が出ることはまずあり得ない。
平成16年度の調査では、残留基準値を超えた食品は0・01%ときわめて少ないので、国産品・輸入品を問わず、わが国の農産物の慢性毒性によるリスクはほとんどないといえる。
(このほか、農薬使用時の基準の遵守、違反の具体例、食品のリスク比較、有機農業や無農薬農業との比較等についての解説があったが、ここでは割愛)
農薬について報道する場合には、その危険性だけを強調するのではなく、農薬を使用しない場合のリスク(収穫量の減少、カビ毒や食中毒の増加、農業の衰退等々)についての正確で科学的な評価に基づいた報道をしてほしい。
農薬工業会では、消費者や報道関係者の疑問や質問に応えるべく、さまざまな情報発信をしているし、つねに窓口を開いて対応しているので、充分に活用してほしい。
■第2部 質疑応答・情報交換
第2部では、当会からあらかじめ提出してあった質問項目、さらには当日の講演を聞いて生じた、次のような質問や指摘に対して、農薬工業会の会員たちが回答したり、それに基づいての議論が行なわれたりした。
- 提出されたデータの一部に、農薬検出違反件数が少なく見えるようなものがあるのではないか。
- おのおの農薬はADI内に収まっているとしても、野菜を多種類摂取するケースでは、農薬同士が相互に影響してリスクが高まることはないのか。
- スライドに「残留農薬基準は安全性の基準ではない」とあるが、それでは、消費者は何をもって「安全性の基準」とすればいいのか。
- 貴会が考える「好ましい報道」という具体例は示せるのか、等々。
時間の関係もあり、充分に議論を尽くせないこともあったが、会員の関心の高いテーマであったため、勉強会としてかなりの盛り上がりがあり、予定時間を大幅にオーバーしての閉会となった。