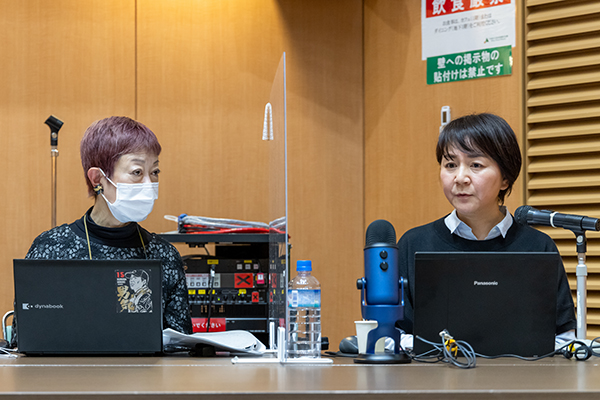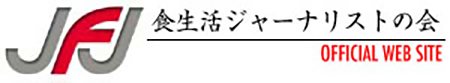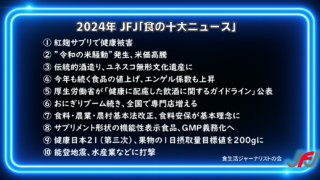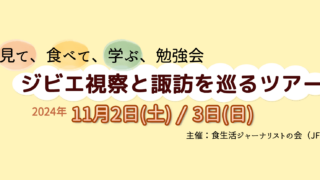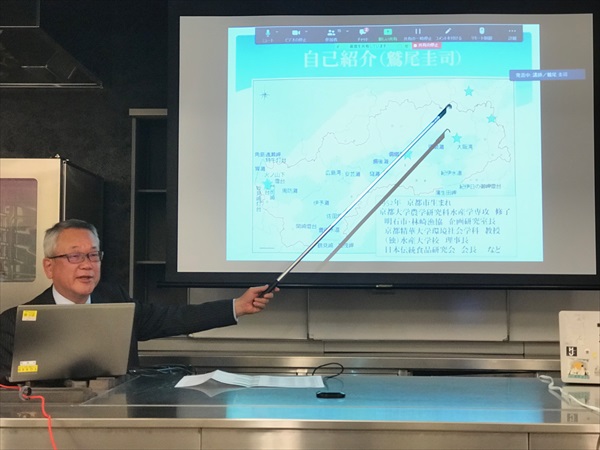・演題:〈シェフたちのコロナ禍〉を語る
・講 師:井川直子(文筆業)
・進 行:畑中三応子(食生活ジャーナリストの会)
・参加者:会場参加9名/オンライン参加30名
・文 責:畑中三応子
**************
『シェフたちのコロナ禍 道なき道をゆく三十四人の記録』(文藝春秋)は、最初の緊急事態宣言下、自主休業するべきか営業を続けるべきか、ほかに道があるのか何をすればよいのか…と、未曾有の事態に煩悶するシェフたちの生々しい肉声の記録である。著者の井川直子さんに、取材のきっかけから本ができるまで、その後の反響などを語っていただいた。

■衝動的にはじめた取材
2020年の3月、飲食店がコロナ感染のもっともリスクの高い場所とみなされ、客が遠のきはじめていたころ、東日本大震災のときに抱いたのと同じ無力感を感じていた。そんなとき、シェフたちが口々にしたのが「何が正解なのかわからない」という言葉。SNSにもこの言葉があふれていた。
彼らにはいま道がない。それに続く言葉を見つけたくて、ほかの人たちがどう考えているか、知りたいのだ。飲食店で働く人たちを近い場所から見てきた第三者の自分にできるのは、さまざまな声を聞き取って文字にして伝えること。それなら書ける。彼らの「何が正解なのかわからない」に向かって歩き出した。
■書記係に徹する
話を聞いたのは、これまで雑誌で取材したことのある主に個人店のシェフや経営者34名。スピード感をもって行数制限なく自由に書くため、個人で発信ができ、なおかつ開かれたメディアであるウェブの「note」に発表の場を定めた。スタートしたのは緊急事態宣言発令の翌日、4月8日。刻一刻と状況が変わる激動の日々ゆえタイトルは「○さん、○月○日の答」とし、筆者の意図はなるたけ入らないよう書記係に徹した。目標は1日1人だったが、結果的には1.6日に1人のペースで書いた。
■見つけた書籍にする意義
5月25日に緊急事態宣言が解除され、段階的に世の中が動き出し、自分の役割は終わったと、5月28日の34人目をもってペンを置いた。文藝春秋から書籍化が決まったものの、正直なところnoteでの連載で完結したと感じていたとき知ったのが、聞き書き文学の傑作『チェルノブイリの祈り』。ノーベル文学賞を受賞したスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチによるこの作品を読み、ウェブの記録はいつか消えてしまうが、50年後、100年後の人々に、いまの私たちの心臓の鼓動まで伝えられるのが書籍なのだということに思い至った。
■心臓の鼓動を伝えるための工夫
どんなに苦しく、痛ましい出来事も、私たちは忘れがちだ。そこで書籍化にあたり、記憶をとどめるためのいくつかの工夫をした。まず、全体を時系列の7章立てにして各扉にその時点での状況がわかるリードを書いた。巻末には2019年12月から2021年1月まで、日本の動き・飲食関連の動き・世界の動きを記した年表をつけた。2020年10月に書籍用の追加取材をし、春は下を向いて苦悩していた彼らが前を向いて立ち上がり、たくましく生きていった道程も記録した。
■想像もしていなかった反響
本が出ると自分では想像もしていなかったほどの大きな反響があり、多種多様のメディアで書評が掲載された。社会に波紋を広げられたのは、コロナ禍で不要不急の筆頭に挙げられた飲食業に従事し、働く誇りを奪われて「何のためにこの仕事をしているのか」と自問自答した彼らの言葉に、あらゆる職業や立場を超えた普遍性があったからではないか。書籍にした意義を実感することができた。
井川さんは最後に「34人の〈答〉は、あのときしか聞けなかった価値のある言葉。50年後、100年後の人々にも響き、役立ててほしいと思う。なぜこの仕事を選んだのか、原点を突きつめていったシェフたちには本当に感銘を受け、自分にとっても道しるべになる本になった」と結んだ。料理人への深い尊敬と愛情をひしひしと感じる勉強会だった。
質疑応答では、井川さんが取材にテープを使わなかったことがわかり、ニュージャーナリズムの旗手トム・ウルフがテープもメモもとらず、あれだけの大作を書いた事実を思い起こさせたことを付け加えておく。