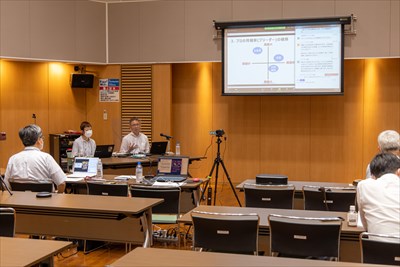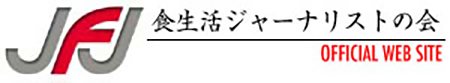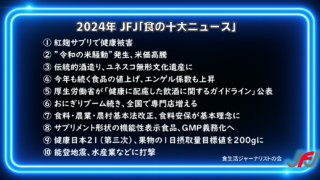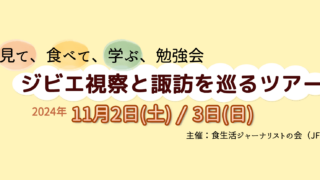・演 題:知られざる育種産業の舞台裏と品種という存在の可能性
・日 時:2022年9月7日(水)19時~20時30分
・講 師:竹下大学(品種ナビゲーター、育種家、技術士〈農業部門〉、J.S.A.ソムリエ)
・進 行:畑中三応子
・参加者:会場参加11名/オンライン参加46名
・文 責:畑中三応子
**************

欧米で“ブリーダー(育種家)”は農業界のイノベーターとして認知されているが、日本では育種という産業自体がよく知られていない。また、ごく一部の食品を除けば農作物の品種に対する消費者の関心はあまり高くない。
日本のトップブリーダーとして育種の現場に長年身を置き、現在は“品種ナビゲーター”として野菜や果物の品種の魅力を一般向けに普及する活動をしている竹下さんに、育種と品種のイロハから現状までを語っていただいた。
まず、1876年(明治9)に「品種」という言葉をはじめて使ったのは当時内務卿の大久保利通、その翌年に日本初の育種場を開設したのは大久保と同じく薩摩藩出身の前田正名だったという歴史的事実からは、育種が殖産興業の重要な事業のひとつと位置づけられていたことが分かる。
今日、プロの育種家には、企業所属(育種会社)、公的機関所属(農業試験場など)、生産者(個人農家)の3パターンがある。本来、品種開発はそれを使って食べる生活者のために行われるべきものだが、実際は生産者優先。種苗(育種)ビジネスはBtoBであり、生産者メリットが消費者メリットより重視される。とてもおいしいが、病気に弱い、収量が少ないなど、生産サイドでの弱点でお蔵入りする品種は少なくないそうだ。
対立構造のように語られることが多いゲノム編集・遺伝子組み換え技術と従来の交雑育種(交配)だが、本来は手段の違いでしかない。前者は最先端で効率的(でも不安)、後者は時代遅れで非効率(ただし安全)と捉えられがちだが、実は品種改良のトータルプロデュース力が高いのは育種家のほうである。これまで両者が協働することは少なかったが、生活者に安全で有益な品種を提供するためには、今後は同じ目的に向かって力を合わせることが必要だという竹下さんの意見にはおおいにうなずいた。
お話の最後を「品種という存在は、食の楽しみをもっと広く、深く、大きくしていくきっかけになる」と結んだ竹下さんからは、品種と育種への熱い気持ちがひしひしと伝わった。