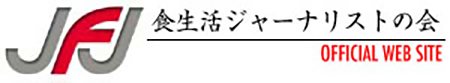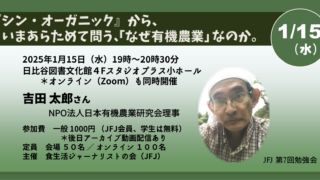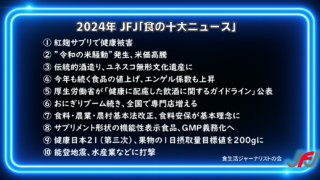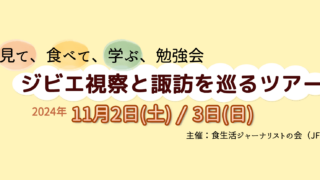【テーマ】「21世紀、日本人は肉を食べ続けるのだろうか
ビーガン、代替肉、培養肉について日本の食文化の中で考える」
【日 時】2024年11月30日(土) 13:30~17:00、懇親会17:00~19:00
【場 所】東京大学農学部フードサイエンス棟中島董一郎記念ホール
(ハイブリッド:Zoom会議)
【主 催】食生活ジャーナリストの会(JFJ)
【参加者】83名(オンライン参加を含む)
今、畜産業は地球規模での試練の時を迎えている。環境負荷を高め、動物福祉を棄損し、畜産業への抵抗が高まる。そして、人口爆発により現状の畜産業では必要なたんぱく質を賄いきれないとの見方もある。明治時代以降、日本人の食肉需要を支えてきた畜産業はどうなるのだろうか。私たちはこれからも肉を食べ続けることができるのだろうか。そもそも、日本人にとって食肉とは? 日本の食肉の歴史を振り返り、未来の食肉のあり方を探る。
【プログラム】
司会:大村美香(JFJ幹事、朝日新聞暮らし報道部記者)
【開会挨拶】
畑中 三応子(JFJ代表幹事)

【基調講演】
原田信男氏(国士舘大学名誉教授)
「日本における『肉食文化』の変遷」

「日本の肉食は明治の文明開化から?」ーー。 古来、日本食はコメ・野菜が中心で、こう思っている人がほとんどなのではないか。原田氏は人類の誕生から日本の古代国家、中世、江戸時代を振り返り、世界でも稀な日本人と肉食との意外な関係を披露してくれた。そもそも、人間が生命活動の頂点に立っているのは、全体重の2%の脳を全エネルギーの20%で支えるために必要な多量のたんぱく質を、道具を作り、狩猟の戦略を立て、火を使って調理することで実現してきたからだという。日本では弥生時代に稲作が始まる。稲作には水が必要なため、魚も獲れ、コメと魚のセットが食の中心となった。ただ、これではたんぱく質が足りないので、世界的にはブタを飼育し始める。しかし、日本の場合、古代国家が“穢れ”を理由に肉食を禁止する。「肉食すると稲作が失敗する」というのだ。科学的根拠はないが、イネは繊細な作物であり、コメは国家の重要な財源であることから、こうしたタブーを作っていったのだろうと推測する。加えて、仏教における殺生禁止も重なった。一方で、全く肉食しなかった訳ではなかったという。古代国家が禁止したのは4月から9月の稲作期であり、牛、馬、犬、猿、鶏という労役にもなる身近な動物に限った。猪や鹿は該当せず、これらはしばしば農地を荒らす。農民は農具として鉄砲の所持が許可される。退治後は当然、ぼたん鍋やもみじ鍋を堪能したという。肉食は、理念と現実とのせめぎあいの中で、穢れを媒介に日本人の中に深く浸透してきたと、原田氏はまとめた。
【パネルディスカッション】
◉大津愛梨氏(O2Farm共同代表)
「21世紀も日本人は肉を食べ続ける! 持続可能な畜産の提案」

大津氏は、熊本県南阿蘇村の約7ヘクタールの農地で稲作とあか牛の繁殖に取り組むO2Farmについて紹介してくれた。O2Farmがある阿蘇地域は全域が環境省の国立公園に指定されており、2013年にはFAO(国際連合食糧農業機関)の世界農業遺産に認定された。草原にあか牛を放牧し、野焼きによって維持、そして稲作にも利用する活火山の麓で1000年以上も続いてきたこの暮らしが、阿蘇のランドスケープを生み育ててきたという。O2Farmでは、このランドスケープを次世代に遺すことにつながる農業、すなわち「ランドスケープ農業」を提案している。
◉杉浦仁志氏(Social Food Gastronomy)
「世界のなかの日本の『ビーガン』」

杉浦氏はビーガンシェフであるが、自身はビーガンではない。海外の一流レストランでの経験を重ねて日本に帰国すると、海外に比べて食の多様性への理解が進んでいないと実感、ベジタリアンやビーガンの食を普及させようと「ソーシャルフードテクノロジー」を標榜し、活動している。具体的には、食を中心に、フードテック、医療、環境、福祉、スポーツ、地方再生などをテーマに産官学の連携に取り組んでいる。ビーガンの市場価値を見ると、デンマークの三つ星レストラン「ゼラニウム」では、野菜だけで9万5000円の料理を提供する。日本では肉料理のコースが高くて5万円ほど。そして、海外の高価なビーガン料理には大抵、日本の懐石料理へのリスペクトが盛り込まれている。日本の消費者にはこうした世界における食の多様性を知ってほしいという。その上で、人それぞれの選択を互いに認め合う社会を期待するという。選択肢がビーガンであろうが、培養肉であろうが、だ。
◉吉富愛望アビガイル氏(一般社団法人細胞農業研究機構代表理事)
「新しい選択肢・培養肉に国、産業界、消費者はどう対応できるのか」

吉富氏は、細胞性食品(培養肉)の日本国内のルール形成を目指す団体の代表だ。団体には、大手食品企業12社をはじめ、スタートアップ企業、ライフサイエンス企業など関係企業50社、アカデミア6人が参加している。日本では販売はまだで、研究開発も一部で行われているだけだが、取り組むのには理由がある。新技術を実用化するに当たって、ルール形成次第でそこから得られる利益が大きく変わってくるからだ。仮に日本では実用化しないことになっても、海外で確立した新規食品市場は、輸入や海外投資において日本は無関係でいられないほどインパクトが大きい。ルールがないと、かなりの不利益を被ると想定する。逆に、この新規食品市場には、日本が持つ食の先端技術や世界に誇る和食文化を生かし、リーダーシップを発揮できるのに、それをしないのは大きな機会損失となる、とも。また、新市場の規模予測にも、日本に材料がなければ難しい。日本が国際的な議論の蚊帳の外に置かれず、国内でのルール形成を推進することが、日本の国益にかなうものと吉富氏は考え、実践中だ。
【クロストーク】

ファシリテーター:小山伸二(JFJ幹事、書肆梓&クラウドナインコーヒー・代表)
クロストークでは登壇者4人によって、日本の肉食のあり方が議論された。歴史家である原田氏は、従来型の農業・畜産業も植物の再生力を生かした循環型として持続すると見る。また、肉がなくても自然の恵みでいくらでもおいしい料理を提供できる植物性代替肉の考えにも賛同。さらに、培養肉でさえ生命の営みの一つとして捉え、研究開発の推進を是とする。人間の生命活動に必要とすたんぱく質としての食肉への需要は今後も変わらないだろうが、想定以上の供給は行き過ぎかもしれないと問題提議もした。
一方、培養肉を含め代替肉などのフードテック推進を期待する杉浦氏は、その理由を「食に多様な社会をつくりたいから」と説明した。例えば、子供の食物アレルギーが増え、学校給食でも代替卵などの導入を急いでいる、また料理人の労働現場が疲弊し生産性向上のためより高い価値の創出が期待されていることなどにおいて、フードテックが貢献するだろうと考える。
議論は代替肉や培養肉の特権化や平等化にも及んだ。吉富氏は現状、コストがかかることから培養肉は高価で特権化せざるを得ないが、将来は地球規模でのたんぱく質欠乏を補うためにも平等を求めるものだと話した。ただ、日本の食文化ブランドが海外で「培養霜降り肉」や「培養黒毛和牛」となり、日本の国益を損なうことのないような取り組みも必要だとした。
最後に原田氏は、「食は貧困問題に関係し、国ごとの格差だけでなく、一国内での格差拡大にもつなっていることを憂いを感じる。肉食を含めて食の問題には一人ひとり声を挙げていかなければならない」と、さらなる議論の必要性を訴えた。

文責:中野栄子(JFJ副代表幹事、ジャーナリスト)