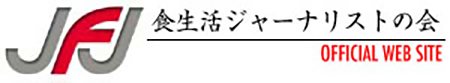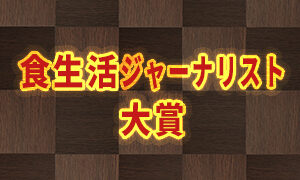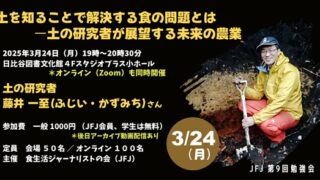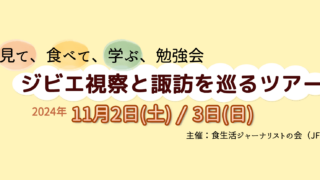・演 題:マチでもムラでも「食べられない」現代日本の食料政策とは?
・日 時:2024年8月26日(月)19時~20時30分
・講 師:平賀緑/京都橘大学経済学部准教授
・進 行:大村美香
・参加者:会場参加16名、オンライン参加31名
・文 責:大村美香
**************

食品の価格高騰が生活を圧迫し、フードバンクや子ども食堂などの食料支援が各地で広がっています。一方、農村部では、経費を下回るほどの低い生産者価格に、「これでは食べていけない」の声が上がります。食べ物が十分あるはずの日本で、「食べられない」悩みが深まっています。いったい、何が起きているのか、食と資本主義経済の関係を研究している京都橘大学経済学部の平賀緑・准教授に日本の食料政策の現状について語ってもらいました。
食料政策は農業政策とは異なる。日本の憲法には、国民に健康で文化的な最低限の生活を保障するということが定められているが、それを実現するための食生活を保障することが食料政策だと考えられる。だが、日本での議論は、国内市場に適正価格で十分な量の食料を供給さえすれば、日本という国はまだ豊かだから大丈夫だというところで終わっている感がある。農業の重要性を否定する意図はないが、農業や食品産業を発展強化させることと、人々の胃袋を具体的に満たして食を保障することは違う。ここが一番お伝えしたいこと。
食料を保障するために農業や食品産業の維持、発展は必要条件だが、農業、食品産業の発展が必ずしも全ての人の胃袋を満たすことには繋がらない。十分条件ではない。そうであれば、食料政策として人々の胃袋を確実に満たすためにはどうすればいいのか。そもそもどんな食をどう保障することを目指しているのかを考えたい。
食べる側の人への支援が不足していると思う。例えば、帰宅して聖護院大根が1本玄関前に届いていたら、うれしいだろうか? 高価な京野菜であっても、私だったら冷蔵庫に入らないし、料理法も分からない。料理するために検索して、長時間で煮なきゃいけない。ましてや、育ち盛りの子どもが2人3人いる1人親で、大抵こうした場合は母親で、パートを複数駆け持ちされているお母さんがこれをもらっても、時間も精神的余裕もない人も多いということを考えていただきたい。
一方で、京都の農業政策としては、農業政策は農家が営業を続けられるようにするための施策なので、当然、付加価値の高い、なるべく高く多く売れるものを作って農業を続けるという政策になる。こうして作られたブランド京野菜は、必ずしも庶民の胃袋を満たすことにはつながらない。
京都のフードバンクの活動に参加したこともあるが、配布する食料品に生鮮品を入れるのは難しく、基本的にやはり加工食品が多くなる。食料支援のアンケートでは、子供たちだけで食べられるものが嬉しいという答えが返ってくる。夏休み中の昼ご飯は簡単にできるものを子供たちで食べさせるので、レトルトやインスタントが助かると。つまりもう親が子供と一緒に食事ができていない。子供のための食事を何らかの形で準備しておいていかなきゃいけない、もしくは子供だけで食べられるものを必要とする状況に追い込まれている人も多い。食べる側に余裕がなくなっている。経済的な面だけでなく、時間的、精神的、余力的、スキル的、全てにおいて、食べる側がきちんと作って食べることができない状態になっている。食べる側の力というのが弱っている現状がある。
しかし日本の政策では、あってもフードバンクや子ども食堂の話ばかりで、根本的な問題に政府がどう対策を取るのかという話は聞こえないように思う。今の日本は食料安全保障をようやく言葉だけでも挙げるようになったが、内容は結局まだ、供給と、あってもアクセスの話になっている。
よく言われることだが、世界には充分な食料があるのに、食べられてない人と、食べすぎて不健康になっている人とがいる。グローバルな食料システムは巨大なアグリビジネスがますます力を強めていて、小規模な農民たちが一番飢えている。その一方で、工業的な農業食料システムが温室効果ガスの4分の1を出し、地球も壊している。こうした、山ほどある問題も、資本主義的には、当然の動きだと位置づけられる。なぜかというと、資本主義経済というのが、人や人のつながり、無償労働、自然など、そもそもお金で計算できない部分から絞り取れるものを絞り取って、お金で計算できる部分を膨らませようという仕組みだから。資本主義経済がまっとうに機能すればするほど、人も自然も壊れていくシステムだから。農業と食品産業もまた、資本主義経済の中での経営事業体であって、いくらかの利潤を上げて経営を続けていかねばならない。そのために作るのはやはり「食べもの」というより「商品」であって、売って儲けられるものを作らねばならない。資本主義的な農業・食料システムが発展した結果、その資本主義のシステムの都合によって、私たちの食べる物、食生活、農業がどう変わってきたかということをおさえておくことが重要ではないか。
コロナ以降、食料配布に来る人たちを見ていると、一見困っていると分からないような「普通の」格好をした若い人、子連れの人、学生たちが多く、貧困の底が抜けたと言われている。金銭が乏しい時、予算が限られている時に、砂糖や油のたくさん入ったカロリーが高くて長持ちし、子供が喜んで食べてくれるような加工食品を選ぶというのは、それは生活の知恵だとも言える。ただその結果選んだものは、食べる側の健康にも、国内農業にとっても、望ましいものにはならない。
具体的にどれだけの人が食料不安に陥っているか、日本の現状について基礎的な調査が足りてない。政府は供給量を把握していても、どういう人がどういうものをどういうルートで入手してどのように胃袋に入れてるか、もしくは食べられていないかいうことの基礎調査がなかなかまだできていない。
食から健康と環境と社会正義に取り組む、フードポリシーという考え方がある。誰が何をいつどうやって食べるかというそこに関わる意思決定全てを幅広く考察する。従って、農業だけではなく、貿易政策、サプライチェーンの企業の動向、企業の戦略、そこで働く人たち、政策、消費者の動向、栄養公衆衛生上の知識、環境問題、科学技術、社会的な問題、文化も当然関わってくる。これら全てが関わって私たちが今日何を食べるかが決められている。
政府や企業は、今までの生産主義では持続不可能だといわれても、イノベーションを中心とした対策を考えがちだが、私たち市民社会側で推し進めたいのは、エコロジー的パラダイムという、環境や地域の生態系や社会を大事にする、生物多様性、自然と人と知識、人々の持っている文化やスキルを大切にしながら総合的に組み合わせて食を確保していくアグロエコロジー的な方向を目指したいと思う。
もう一つ紹介したいのがフードポリシーカウンシル。トロントなど北米で取り組まれている活動で、行政と市民社会、企業、事業者、生産者を含めて、住民がきちんと食べられるような食の都市計画として考えようというもの。以前、トロントのNGOを訪ねたことがある。かなり予算を取って新鮮な野菜や牛乳・卵など必要なものを購入してフードバンクもしているが、それが難しい人たちにはドロップインという、そこに行けば年齢も収入も関係なく誰でも暖かい食事を食べられる食堂があって、その隣には様々な問題を相談する窓口が作られている。まずお腹を満たしてからお金の問題や、住まいの問題、雇用の問題や困っている法律的な問題を窓口で相談できる。そこの施設では、いかに安く栄養価の高い食事を作るかというスキルを養う料理教室もやってるし、ファーマーズマーケットもやっている。カナダは多民族国家なので、民族ごとの畑ということで、フィリピナの畑、チャイニーズ畑、ラティーノ畑という、それぞれの食文化も大切にしたコミュニティガーデンがある。総合的な取り組みで、その地域に住む人たちの食と生活を支えようとしている。
食べる側も、いつまでも受け身の消費者だと、まともな食を確立する食料政策はできない。その地域で食を育て、その地域の人たちが主体的に食を確保する視点も必要になる。最終的には、市民が小さく緩やかに繋がって、地域に根指した食と農と経済のネットワークを築くことが重要だと考えている。ただ、そのまともな食生活を実現するためには、真面目に働けばまともな生活ができる労働環境、経済社会が必要だということはもうずっと昔から言われている。上辺の経済成長だけではなく、経済というものが元々「経世済民」、世の中を治め人民の苦しみを救うことが目的だったという基本から立ち戻るべきではないか。広い意味で総合的に食を確保することを考える食料政策を、日本でも考える人が増えていくきっかけになれたらと願っている。