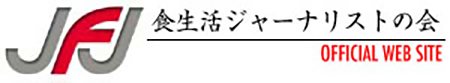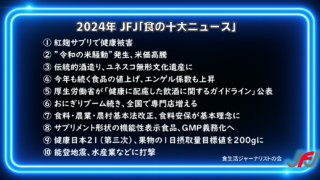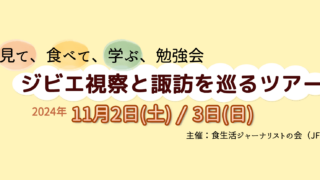キッコーマン株式会社代表取締役社長 茂木友三郎氏
今年の5月10日、上海郊外の昆山市(人口約60万人)にしょうゆ工場をオープンしました。キッコーマンの海外工場としては、1973年(昭和48)のアメリカ、ウィスコンシン州に始まり、シンガポール、オランダ、そしてカリフォルニアと続いてきた海外進出の5番目となります。
キッコーマンが国際市場へ目を向け始めたのは、昭和30年代の初めです。実は当時、しょうゆ単体の売上げは全体の8割を占めていたのですが、作れば売れる時代は去って、国内需要が頭打ちになり、しょうゆの国際化が必要となっていました。
昭和32年、サンフランシスコにキッコーマン・インターナショナルという販売会社を設立。これには重要な海外のマーケッティング戦略の転換があります。戦前、しょうゆの輸出相手は、海外に住む日系人でした。戦後は、日本にやって来た外交官、ビジネスマン、軍関係の人々、ジャーナリストなどがしょうゆの味を覚えて帰国し、アメリカにはしょうゆを受け入れる下地がすでにあったのですが、それを、一般のアメリカ人に買ってもらおうというのです。
しょうゆの味を覚えてもらうための、スーパーでのデモンストレーションに始まり、ホームエコノミストによるレシピの開発、新聞誌上での発表などのプロモーションを経て、いよいよ次は広告です。「目立つものを、地域的に」がねらいでした。ちょうどアメリカの大統領選の時期で、国民大多数の目がテレビに向けられます。
その開票速報に合わせてコマーシャルを打った結果が大成功で、しょうゆが大手スーパーのセーフウェイにおかれるようになりました。以後は順調に販路を伸ばし、40年代後半になって現地工場の設立までこぎつけたのです。
さて、なぜウイスコンシン州を選んだかというと、その立地です。シカゴの近くにあって交通網が非常に発達していること。アメリカでも有数の穀倉地帯であり、原料である良質の大豆・小麦がとれること。そして、労働力。この三点です。また、この州は犯罪率が低いことも理由の一つでした。現地に工場を作るにあたっては、①経営の現地化(現地の企業と取引を行なう)。②従業員はなるべく現地で採用する。日本からの駐在員は分散して住まわせ、いわゆる「日本人村」を作らずに、現地に融けこむこと。が方針でした。グラスルートからの生産が25年後に10倍の出荷となるようになったのは、現地主義の方針がしっかり根付いたからだと思っております。
現在、キッコーマンのしょうゆは100カ国で販売されていますが、私は「しょうゆを売るということは、文化の交流である」と考えております。ヨーロッパ人がしょうゆを知ったのは、18世紀フランスの『百科全書』の記述が最初ですが、それから2世紀半、世界の歩みの中で、しょうゆはどういう認知をされ、位置にあるのか。それぞれがすぐれた食文化を誇るヨーロッパ諸国では、現在のところ、しょうゆを通した文化の交流の段階であると言えるでしょう。これに対して、すでに40年以上もしょうゆに接してきたアメリカとは融合の段階に達したと考えております。私がかつてワシントンポストの取材を受けたとき、取材記者が「私はKIKKOMANという会社が日本の企業とは知らなかった」と語ったことが、いみじくもそれを表していると思います。
(まとめ:関根悠子)